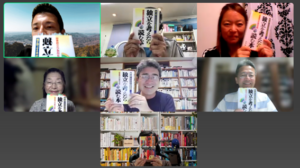井上紗樹さん(比企大25春)の想いと今後やっていきたい活動について、先輩(比企大24秋)の貝津美里さんが、インタビュー記事にまとめてくれました。
誰もが「お風呂」を楽しめる社会、一緒につくりませんか?
― 医療的ケアが必要な子どもと家族のために ―
「今日もお風呂に入ってさっぱりしたね」
お風呂に入れば、誰もが自然と笑顔になる。湯気に包まれてほっと息をつき、身体を洗って心まで整う。1日の疲れを癒す、日常に欠かせない大事なひととき。
けれど、医療的ケアが必要な子どもとその家族にとって、お風呂は常に「緊張との隣り合わせ」であることをご存知でしょうか。
私はこれまで15年間、障がいのある子ども、医療的ケアが必要な子どもたちと関わってきました。そこで目にしてきたのは、「当たり前の暮らしを諦めざるを得ない」親子の姿です。
「お風呂に入りたい」「わが子をお風呂に入れてあげたい」───そんなささやかな願いさえ、支援の仕組みからこぼれ落ち、叶えられない現実があります。
だからこそ私は、障がいや医療的ケアの有無にかかわらず、誰もが安心して「お風呂」を楽しめる社会をつくりたい。その願いを胸に、一歩を踏み出しました。

24時間365日、終わりなき子どもの介護…。
医療的ケアが必要な子どもの親御さんは、毎日絶え間ない介護を担っています。
特に入浴の介助には、大きなリスクが伴います。水滴が気管につながる管に入ってしまう、水が身体に開けた穴に入り込む、管が外れる。不測の事態は命に関わります。加えて、介助する親自身が腰や腕を痛めてしまえば、生活そのものが立ち行かなくなります。子どもが成長しても手が離れることはなく、介護に終わりはありません。体力的にも精神的にも限界が押し寄せてきます。
そこに追い打ちをかけるように、「頼れる場所が少ない」という壁が立ちはだかります。医療的ケアがあるという理由だけで、福祉サービスや施設利用を断られることは珍しくありません。利用先が見つからなければ、すべてを親だけで担うしかない……。
医療従事者ではない親御さんが、子どもの命に関わる事態にも対応しなければならない。そこにどれほどの危機感や不安を募らせているか、どれほどの負担がかかっているか。想像を絶するものがあるでしょう。
子どもの笑顔のために、お風呂に入れてあげたい親心
それでも、多くの親御さんは子どもをお風呂に入れてあげたいと願います。なぜなら、医療的ケアが必要な子どもにとっても、お風呂にはたくさんの良い効果があるからです。
湯船に浸かることで筋肉の緊張が和らぎ、呼吸がしやすくなります。痰が出やすくなったり、胸が広がって深い呼吸ができるようになったり。皮膚や関節の状態を確認する機会にもなり、褥瘡(じょくそう)や脱臼の予防、早期発見につながります。
そして何より、お風呂に入った子どもの表情は驚くほど柔らかく、笑顔になるんです。体が温まり、全身の筋肉が緩むと、自然に笑顔が生まれる。その笑顔を見た親御さんも、笑顔になる。お風呂は「笑顔の循環」を生み出す時間なのです。
入浴介助の負担は大きい。それでも「子どもの笑顔が見られるなら」と、力を振り絞る。そんな親御さんたちを、たくさん見てきました。

「お母さんは、お母さんだけに専念すればいいんだよ」
私自身、シングルマザーとしてふたりの子どもを育てる母親です。
子どもが不登校になったときは、「誰に、どこに助けを求めればいいのかわからない」という心細い経験もしました。フルタイムで働きながら子どもと向き合う日々は、想像以上に大変です。心身ともに限界で、親子ともども笑顔を失っていきました。
そんなとき、友人からこんなことを言われました。
「お母さんは、お母さんだけに専念すればいいんだよ」
その言葉に、ハッと目が覚めました。
”人に頼れるところは、頼っていい。その代わり、私は母親にしかできないことをしよう”
予定通りに物事が進まず、家の中でずっと怒っているくらいなら、いっそのこと他の人に任せてしまえばいい、気づいたのです。自宅で勉強を教えたり、毎日お昼を用意することに負担を感じる。それならば学習支援を行う施設を探し、食事は宅配サービス食事サービスを利用しようと、専門家やプロに任せることにしました。
すると、まず母親である私に余裕が生まれました。子どもの話に耳を傾け、気持ちにじっくりと向き合う時間ができました。すると徐々に子どもも安心した表情になり、笑顔を見せてくれるようになったのです。これこそが、「母親である私にしかできないこと」だったのだと気づきました。
”親が全部を抱え込む必要はない。専門家やサービスに一部を委ねることで、親子のかけがえのない日常は守られる”
それは障がい児や医療的ケア児を育てる親御さんにとっても同じです。

「お風呂を安心して任せられる」親と子の居場所をつくりたい
ほんの30分でも休めるだけで、子どもに笑顔で向き合える。終わりの見えないケアに疲れ果てても、安心できる居場所や支援があれば救われる。一緒に介助をしてくれる第三者がいるだけで、気持ちが楽になる。
だからこそ今度は私が、助けを求め孤独を感じている親子の居場所になりたいと思うのです。その中でも、特に介助の負担が大きく、本来なら日常の癒しである「お風呂」は、専門家やサービスの手を借りてほしい。ほんのひとときでも、親御さんが肩の荷を下ろし、子どもと笑顔で向き合える時間を増やしてほしいと思っています。
けれど今、制度や支援はまだ十分ではありません。医療的ケア児やその保護者が、安心安全に気軽に集える場。入浴介助とそれに伴う医療的ケア。保育所、学校等への訪問。校外学習や修学旅行などへの同行など、看護師が保育所・学校・スクールバス等に出向いてサービスを提供したり。さらには子ども食堂ならぬ、「医療的ケア児や障がい児のための子ども銭湯」があってもいいかもしれません。
私自身も、まだまだ悩みながら支援の仕方を模索しています。だからこそ、あなたの力が必要です!
どうか一緒に、“お風呂が当たり前に楽しめる社会”をつくりませんか?

●印刷用資料
このブログに掲載後、さきさん、美里さんからメールを頂きました。許可を得て転載します。
===
○さきさん
関根さん、美里さん、おはようございます。
記事をブログに掲載してくださってありがとうございます。
今朝はよしきさんがFacebookに添付してくださったりと、先輩方の発信力には本当に感謝しております。
カラー印刷版のチラシについては、10月に間に合うように、印刷の手配を済ませました。出来上がるのが今からとても楽しみです。
あれから、私の方ではいくつかの出会いがありました。一人目は『熊谷市重症児の親の会』の方です。ご挨拶に行き、過去に親たちでお風呂をどうにかしようと施設を借りて試みていたけれどすぐにコロナで断念したと教えていただきました。チラシができたらぜひ欲しいと言っていただいてます。この方は、似たような取り組みをしている他県の例や、鴻巣市と東松山で医療的ケア児に力を入れている施設があるから、そこに相談に行ってみては?などたくさんのアドバイスをくださいました。
2人目は『地域支援センター』の方で、この方は想いにご賛同くださって「行政の会議で紹介してあげるよ」と言ってくださいました。その際に出来上がったチラシも渡していただけるようお願いしてみようと思います。
3人目は埼玉県北部の『医療的ケア児コーディネーター』の方で、「医ケアキッズ支援会議で紹介してあげる」と言ってくださいました。
肝心の【機械浴設備を貸してくれる施設】はまだ見つけられていませんが、これからやろうとしている事を伝えてこられただけでもオッケーと思うようにしています。
先方にアポを取って、足で歩いて出向くとなると日程調整などもありすぐに動けないもどかしさがありますが、SNSではあっという間に届けられる、本当に便利だなぁと思います。
後輩育成基金からこんなにも素敵な記事を作っていただけたことに、感謝申し上げます。ありがとうございました。
比企続きよろしくおねがいします。
さき
○美里さん
さきさん、関根さん
その後も着々と仲間を増やしアクションをし続けているサキさん、本当に素敵です!
私も、七転び八起きで諦めずに頑張っていこうとエネルギーをたくさんいただきました。
チラシも自信を持って堂々といろんな方に渡してきてくださいね!
サキさんなら、きっといい出会いにたくさん巡り会えると思います^^心から応援しています。
関根さん
ブログの掲載もありがとうございます!
サキさんへの応援を通じて、私もとてもパワーをもらいました。人を応援すること、誰かの役に立つことが、働く喜びだということを、改めて感じさせていただきました。顔の見える関係性や一緒に学ばせていただく比企大というコミュニティでだからこそ、感じられたことのように思います。本当にありがとうございました。
比企つづきどうぞ、よろしくお願いします。
美里
===